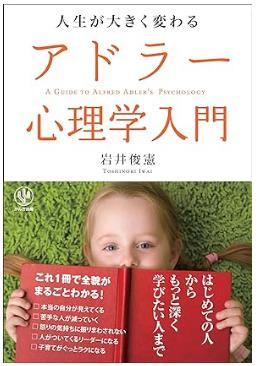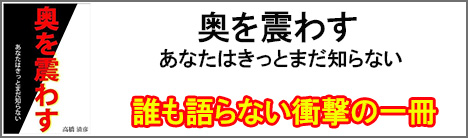気づけば20分でも30分でもぺちゃくちゃ喋って(しゃべって)全然仕事をしない人っていますよね。
もしかして、あなたじゃないですよね?
そんな仕事をしない同僚・部下・上司には絶対に負けない方法とは・・・
-
-
仕事で失敗をした人は3秒だけしても良い事とは
人はなぜ仕事をサボるのか
人間誰しも怠け心(なまけごころ)はあるものです。
「楽してお金儲けしたいな~。」
「宝くじが当たったらこんな会社辞めてやるんだ。」
「早く休みの日がこないかなぁ。」
などなど・・・。
わしなんて毎日思ってますよ。(笑)
しかし仕事をした対価(たいか)として給料をもらっているんだから、サボるのはちょっとねぇ。
サボった分だけ給料を減らされたら、たまったもんじゃない。
だから頑張りますよ。
でもサボった事がバレなければ・・・。
そんな事を研究した学者さんがいたんです。
マクシミリアン・リンゲルマン(Maximilien Ringelmann)というフランスの農業工学の教授。
(・・・色んなサイトにドイツって書いてあるけどフランスです。)
このリンゲルマン、農業機械の開発・研究を行っていたんですが、1913年に自分の生徒にある実験を行いました。
その実験とは、一人対一人のロープの引っ張り合い(日本の綱引きの様なものです)。
これを100%の力(ちから)だと仮定して、二人対二人、三人対三人と人数を増やした時にどのくらい変化するかというもの。
実験の結果はというと・・・
1人対1人---100%
2人対2人---93%
3人対3人---85%
4人対4人---77%
5人対5人---70%
6人対6人---63%
7人対7人---56%
8人対8人---49%
なんと8人が協力して行う綱引きでは、半分ほどの力しか発揮(はっき)していなかったのです。
しかも生徒たちは100%の力を出していると認識していました。
その後もリンゲルマンは、荷車(にぐるま)を引く、石臼(いしうす)を回すなどを行いました。
また二人のチアリーダーに大声を出させる実験では、一人の時に出した声量を100%とした時ペアで出した声量は94%だったそうです。
集団では人間は他人に依存(いぞん)して手抜きをする、これを『リンゲルマン効果』と言います。
これは社会心理学の初期の発見の一つです。
これにより、リンゲルマンは社会心理学の創始者として後世に名前が残りました。
と、まあここまでは情報ですので、堅く書きました。
いや~サボるんですわ。人間って。
大人数になればなるほどサボりますわ。
しかも自分は全力でやってると思っている。
ダメだこりゃ(長さん)
リンゲルマン効果の解決法
本人が全力を出していると思っても、無意識では勝手に手抜きをしている。
これを何とか改善する方法はないものですかね。
何故勝手に手を抜いてしまうんでしょう。
まずは会社などの集団で、自分の努力が正当に評価されていないと感じると手を抜きたくなりますよね。頑張っても、手を少しぐらい抜いても、給料が一緒だったらどうでしょう。
はい。少し手を抜きます。
そうですね。
そう考える人が多いのが現実です。
では自分の努力が正当に評価されたら・・・
手は抜かなくなります。
サボっている事がバレたら・・・
手を抜かなくなります。
社長や役員、人事部長などの偉い人が見ていたら・・・
手は抜かなくなるでしょう。
環境のせいにしているわけではなく、環境を味方にしようという事です。
・自分の努力が正当に評価されていると信じる
・バレてしまうので手を抜かないようにする
・偉い人が横で見ていると思い込む
出来る人は常にこういう自己暗示をかけてるんじゃないでしょうか。
一朝一夕(いっちょういっせき)で出来るものじゃないですが、成果は必ず表れます。
そこに成長があるんじゃないかな。
-
-
転職をしても働かない人のたった1つの法則
サボるって
実は『サボる』の語源はフランス語なんですよ。
へぇ、へぇ、へぇ、へぇ、へぇ、へぇ。
あっ、知ってました?
っていうかまたフランス!?
フランス語のサボタージュ(sabotage)から来たんですって。
で、サボタージュも木靴きぐつ)のサボ(sabot)から来たって話です。
最近の若い女の子たちに人気のサボサンダルの、あのサボです。
諸説あるんですが、仕事をサボって木靴で機械を蹴っていたとか。
木靴だと作業効率が悪いからとか。
機械が上手く動かないので、木靴で叩いていたとか。
木靴で機械を蹴って壊したからとか。
まあ、それでサボ➡サボタージュ➡サボるとなったみたいです。
へぇ、へぇ、へぇ、へぇ。
あっ、うざい!?
しかも日本で流行って使いだしたのが大正時代ですよ。
ビックリですよね。そんな昔から『サボる』って使ってたの?って感じです。
へぇ・・・すいません。
まとめ
無意識は意識で対処(たいしょ)できますよ。
だって、癖(くせ)だって、直せるんですから。
仕事をサボるやつを見るのではなく、自分に出来る事を自分に課していきましょう。
サボるやつが部下や同僚ならこっちのもの。
ぶっちぎりで引き離してやっちゃいなさいな。
えっ?サボる上司?
ダメな上司の撃退法は、またの機会にでも・・・威張る(いばる)上司の対処法とは
無料版のおすすめ
一人でも多くの人に読んでもらいたいので、BCCKSさんで無料公開しました。
Dataとして手元には残らないですが、上記のリンクから無料で読むことが出来ます。
『本をよむ』をクリックすると、新たなブラウザが立ち上がります。
『無料でよむ』をクリックすると、その場所に表示されます。
右に出るカーソルを押すと、次のページに進みます。
何卒よろしくお願い致します。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。